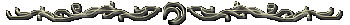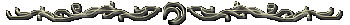
…………僕は月を見ていた。 広がる夜空にぽつんと浮かぶ月。とても寂しそうで、 見ている僕の心をせつなくさせる満月。 淡い輝きを放つ満月は、言葉にならないくらい美しく、 僕は目を離せずに、ただじっ、と見上げている。 それに応えるかのように月も優しく僕を見下ろしてくれていた。 サアァァァーーーーー…… 僕たちの間をそよ風が通り過ぎていく。 穏やかに吹く風は、広大なススキ野原を揺らしながらどこまでも流れていった。 「なにをしているの?」 不意に鈴の音のような声が僕の耳に届いた。驚いて振り返ると、いつのまにか真後ろに 一人の少女が立っていた。 いつからいたんだろう……。 戸惑いながら、その少女を凝視する。 鮮やかになびく金色の髪、雪のような肌に愛らしく映える紅の唇。 優しい輝きを帯びている黒い瞳。 まるで昔聞いた物語に出てくる妖精でもあるかのように、その姿は美しく、 少女を包む雰囲気も普通の人間とはどこか違う、純粋で不思議な印象を僕に与えた。 「君はっ……?」 驚きを隠せずにいる僕に、少女はにっこりと笑った。 「ねっ、何をしていたの?」 僕の疑問を無視して、少女は無邪気に聞いてくる。 「……月を見ていたんだ」 僕が素直に答えると、少女は不思議そうに首を傾げて聞き返してきた。 「……月を?」 僕はうなずく。 少女がなぜ、そんな不思議そうな顔をするのかわからなかった。 不意に、少女が空を指して言う。 「月なんて出ていないのに、あなたは月を見ていたって言うの?」 ──── えっ、月が出ていない? そんなことあるわけないっ!! 僕は確かに月を見ていたんだ……。 少女の言葉を疑いながら、しかし少女の真剣な表情に気づいて、もう一度空を見上げる。 「 ──── そ、そんなっ……」 愕然とした思いが僕を包み込む。 月がどこにもない……。 永遠と続く夜空に光り輝く星は幾千とあるけれど、あの美しかった 月はどこにも見当たらなかった。 動揺する僕に少女は、「ねっ!」と笑顔を見せるとその場に座り込んだ。 「確かにあったんだよっ! 満月が……。僕はそれを見ていたんだっ」 ススキを一本、一本摘み始めた少女に、僕は訴えるように言った。 「仮に月があったとして、あなたはなぜこんな所で月を見ていたの?」 手を動かしたまま、少女は優しい口調で僕に聞く。 「それは…………」 思わず言葉に詰まった。 言いかけたその先の言葉が、続かないことに気づく。 なぜ……? わからない。 こんな所で……? やっぱり、わからない。 僕はどうして、こんな所にいるんだろう……。 どんなに思い出そうとしても、僕の中の記憶はまるで霧でもかかっているように 真っ白だった。 「きっ、君はどうしてこんな所にいるの?」 答えられないのを誤魔化したくて、僕は逆に彼女に聞き返していた。 「私は見ての通り、ここにススキを摘みに来たのよ。部屋に飾ろうと思って」 「ススキを? 」 彼女の手の中に摘まれたススキを見て、僕は不思議な想いに捕らわれた。 君にならもっと可愛らしくて、綺麗な花の方が似合うと思うけどな……。 僕のそんな想いを読みとったのか、少女は風に吹かれ、優しく揺れるススキを慈しむように 見ながら、教えてくれた。 「ここのススキはね、気持ちを楽にしてくれるのよ。嫌なことや、悲しいこと。そういった 感情を忘れさせてくれるの。とても優しい気持ちにしてくれるのよ」 少女の言葉が、僕の心にゆっくりとしみ込んでいく。 (嫌なことや、悲しい感情を忘れさせる……?) 僕は首を傾げてみた。 その言葉がなぜか、引っ掛かった。 「……あっ、そうか。わかった!」 黙り込んでいた僕を見ていた少女が、突然そう叫んだ。 「ススキよっ、ススキ!」 嬉しそうに言う少女の顔を僕はわけも分からず、ただ見つめる。 「ススキがどうかしたの?」 僕が聞くと、少女は両手いっぱいになったススキを落とさないように気をつけながら、 しっかりと持って立ち上がった。 「あなたはきっと、ここのススキたちに記憶を忘れさせられたのね。 悲しいとか、そんな感情になったあなたにススキたちが気づいて、ここに呼び寄せたの。 その感情を忘れさせようとしたんだけど、それはあなたの記憶が関係してて、 だからその感情を忘れさせるためにあなたの記憶ごと忘れさせてしまったのよ」 なんだって ―――― ? そ、そんな馬鹿なこと……。 ススキが記憶を忘れさせる? 僕を呼んだ? 信じられない。 「信じられないなら、思い出してみる?」 僕の表情から、その思いに気づいたのか、少女は言った。 「でも、忘れたはずの悲しい感情とかが、戻ってくるのよ。それでもいい?」 少女の言葉を信じることのできない僕に、少女は優しい口調で言い、今まで以上に 真剣な顔を見せる。 もしも、少女の言っている言葉が本当なら。たとえどんな感情を思い出そうと、僕は 記憶を取り戻したい。 その記憶の中に、何か大切なものがある。そんな気がするから……。 だから僕は頷いて、記憶を取り戻してほしい、と少女にお願いした。 少女は優しく笑って、頷く。 「じゃあ、ゆっくり目を閉じて」 僕は少女の言うとおり、そっと目を閉じる。細い少女の指先が額にあたるのを感じた。 ……僕の中に眩しく輝く光があふれた。 |