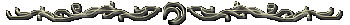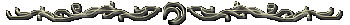
―――― 頭の中に少しずつ、ぼんやりと映像のようなものが現れてきた。 一人の少年が声を荒げ、白衣を着た人に言葉を投げつけている。 『先生っ、瑞穂は……。あいつは助かるんですかっ!?』 あれは、……僕? その少年は僕にそっくりだった。 ……いや、あれはきっと僕自身なんだろう。 そんな気がしてならない。 僕の言葉を悲しそうな顔で受け止める先生は、黙ったまま首を振った。 どうにもならないと ――――― 。 僕は愕然となり、その場に座り込んだ。 『……嘘だ。たった一人の妹なのに……どうしてっ!?』 涙がこぼれていた。 声をたてずに、泣く。 『先生っ! 大変です!! また発作が』 『なにっ!!』 瑞穂の様子を看ていた先生の助手が、部屋の中から叫ぶ。 先生もあわてて部屋に戻っていった。 それから、三十分くらい経った頃。 先生が出てきて、僕に残酷な言葉を突き付けてきた。 『瑞穂ちゃんは……。もって、二日だろう』 もって、二日。 ――――― ミズホノ イノチガ タッタ ソレダケ ―――――― そんなの、そんなのっ! 『嘘だぁ ――――――― っ!!』 先生が引き留めるのも聞かず、僕は叫びながら家を飛び出し、夢中で走った。 ただ、がむしゃらに……。 どこをどう走ったのか。 そんなことさえもわからなくなるくらいに、僕は走り続けた。 ……どれくらい経っただろうか。 走るのをやめて、とりあえず乱れた息を整えた僕はゆっくりと周囲を見回す。 小道ばかりが永遠と続いて、辺りは草でいっぱいだった。 空に浮かぶ満月の光が、それらと僕を優しく包み込んでくれていた。 僕はそのまま、両膝を地面につけた。 ……ひたすら、祈りを捧げる。 『神様、どうか妹を助けてください』 両手を組み合わせ、心から真剣に祈った。 両親を早くに亡くし、それでも僕たちはお互いを心の支えにして生きてきた。 妹がいたから、僕はここまで頑張ってこれたんだ。瑞穂を守るために……。 その妹が死んだりしたら、僕は……。僕はっ!! 堪えていたはずの涙がまた、あふれだした。 頬を伝わり、次々と流れ出す。 『 ―――――― っ!?』 涙をこぼし悲しみくれる僕の耳に、歌声のようなものが届いた。 辺りを見回してみる。 (誰もいない……?) 最初はかすかだった歌声が、少しずつ大きくなってきた。 僕はそれに導かれるようにゆっくり、歩き始めていた。 美しく響く、歌声のもとへ ―――――― 「思い出したっ!!」 僕は大声を上げながら、目を開けた。 「そうだ……。僕はたった一人の妹が死んでしまうと言うことに絶望を感じて、 家を飛び出してきたんだ。それから……。歌声が聞こえてきて、それに導かれるように 歩き出した。そして、気がついたらここに来ていたんだ」 ――――― それから、君に会った。 僕の言葉を聞き終えると、少女は「やっぱりね」と納得したように頷いた。 (よかった、思い出すことができて………。) 安堵する僕と少女の間を、風が優しく吹き抜けていく。 少し考え込むようにうつむいていた少女が、顔を上げて僕に言った。 「そろそろ、帰った方がいいわ。きっと妹さんが会いたがってるわよ」 「…………うん。帰るよ……」 僕がぽつんと返した言葉は、もう少しで消え入ってしまいそうなくらい小さなものだった。 「そうだ……。ついでにここで会った記念にこの花をあげる」 少女はそう言うと、両手いっぱいのススキを何とか片手で抱えて、自由になった方の手を 自分が着ている黄色のワンピースのポケットの中に入れた。 次にその手がポケットから出されたときには、金色に輝く華が一輪、握られていた。 「月華草っていうのよ。珍しい花なんだけど、そうね。あなたの妹さんの側にいた お医者さまなら、知ってるかも」 意味ありげな言葉を口にしながら微笑む少女は、その月華草という花を僕にくれた。 綿帽子のようにフワフワしているその花は、しかし吹き付けてくる風に飛ばされることもなく 月の光のような美しい輝きを放っている。 僕は今まで、こんなに神秘的な花を見たことがなかった。 とてもこの世のものとは思えない。 「じゃあ、途中まで送ってあげるわ」 花を見つめる僕に、少女が言う。 僕は花から視線を外して、少女の黒い瞳を見て頷いた。 「ありがとう……」 お礼を言う僕に少女は本当に、嬉しそうに笑った。 その笑顔を心に刻み込む。 「もう一度……、目をつぶって」 言われた通り、僕は目をつぶった。 「さようなら」 少女の最後の言葉が僕の耳に届いた瞬間、僕の中は眩しいほどの光で いっぱいになった。 |